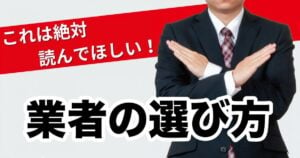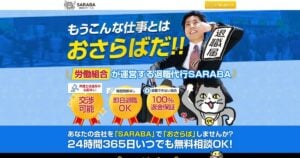新卒で入社してすぐ、職場の環境や働き方に違和感を覚え、退職代行を検討する人が増えています。退職を伝えたくても勇気が出ない状況は珍しくありません。
 LiNee編集部
LiNee編集部退職代行は、新卒が入社してすぐに辞めたいと感じたときに有効な手段として注目されています。
迷いや不安を解消し、納得のいく選択をするための参考になります。
新卒でも退職代行は使える?サービスの基本と注意点
新卒社員でも退職代行サービスを利用することは可能です。労働基準法では、退職は労働者の自由な権利であり、新卒であってもその例外ではありません。入社後すぐや研修期間中でも、退職代行を通じて正当な手続きを踏むことができます。実際に利用する際には、利用の可否やリスク、サービスの違いについて正確に理解することが大切です。
- 新卒でも退職代行の利用は法律上問題ない
- 入社すぐや研修中でも利用できる
- 退職代行の選び方によって結果が変わる
- 弁護士・労働組合の運営元であるか確認が必要
新卒が退職代行を使うのは問題ない
退職は労働者に認められた基本的な権利であり、新卒であってもその権利に変わりはありません。退職の意思は原則として自由であり、民法627条に基づき、2週間前に退職の意思を伝えれば一方的に契約を終了させることができます。
 LiNee編集部
LiNee編集部退職代行サービスを利用することにより、会社と直接やりとりすることなく退職の手続きを進めることができます。新卒であることを理由に退職を拒否することは法律上認められていません。
新卒に対して精神的なプレッシャーをかけて引き止めようとする会社もありますが、退職代行を使えば第三者が対応するため、そうした不安を回避しやすくなります。
入社してすぐや研修中でも可能?
入社直後や研修期間中であっても退職代行の利用は問題ありません。法律上は労働契約が開始されていれば、退職の自由は保証されており、利用の時期に制限はありません。
実際に入社から1ヶ月以内で退職代行を利用する新卒社員は増加傾向にあります。特に毎年4月から6月にかけては、精神的な負荷や労働環境のギャップを理由に依頼が急増しています。
多くの退職代行サービスは、入社から何日目であっても即日対応が可能で、申し込みから数日で退職が完了するケースもあります。状況が厳しい場合は早めの対応が望ましいです。
通常の退職との違いと退職代行サービスの役割
通常の退職は本人が上司に直接退職の意思を伝えますが、退職代行では専門業者が本人の代わりに退職意思を会社へ伝達します。この代行は、精神的なストレスを軽減し、円滑な退職をサポートすることが目的です。
退職代行サービスには大きく分けて3つの種類があります。一般企業が運営する民間型、労働組合が運営する組合型、弁護士が直接対応する弁護士型です。法的トラブルに発展する可能性がある場合は、弁護士が対応するサービスが適しています。
以下の表は、それぞれのタイプの特徴を比較したものです。
| 運営元 | 主な特徴 | 法的対応 | 費用相場 |
|---|---|---|---|
| 民間業者 | 価格が安く即日対応も可能 | 交渉不可 | 約2〜3万円 |
| 労働組合 | 会社との交渉が可能 | 一部対応 | 約2.5〜3.5万円 |
| 弁護士 | 内容証明・損害賠償請求にも対応 | 法的対応可 | 約5〜8万円 |
選ぶサービスによって対応範囲が異なるため、自分の状況に応じた選択が求められます。
新卒の退職代行サービスの利用実態
退職代行サービスの利用は、2024年度の新卒世代の間で確実に広がっています。精神的な負担の軽減や、短期間での退職手続きが可能な点から、多くの新卒が選択する手段となりつつあります。最新のデータからは、利用者の傾向や背景、理由が明確に読み取れます。
退職代行の利用者数の月別推移(2024年4月~2025年2月)
2024年の4月から5月にかけて、退職代行サービスの新卒利用件数は急激に増加しています。特に5月は入社後の配属先が決まり、実務が始まる時期であることから、現実とのギャップに直面して退職を決意するケースが多くなります。
以下は2024年4月~2025年2月の新卒利用者数の月別推移を示した表です。
| 月 | 利用者数(名) |
|---|---|
| 2024年4月 | 256 |
| 2024年5月 | 298 |
| 2024年6月 | 251 |
| 2024年7月 | 211 |
| 2024年8月 | 175 |
| 2024年9月 | 112 |
| 2024年10月 | 113 |
| 2024年11月 | 65 |
| 2024年12月 | 97 |
| 2025年1月 | 118 |
| 2025年2月 | 118 |
特に5月と6月の利用者が多く、配属や業務内容の実態を知ったうえで早期退職を決断していることがわかります。
性別・職種ごとの利用状況
新卒で退職代行を利用するのは男性の割合がやや多く、全体の約56%を占めています。職種別では、サービス業・営業職での利用が突出しています。体力的・精神的な負担が大きい仕事や、対人関係が密な職場での利用率が高い傾向にあります。
| 性別 | 利用割合 |
|---|---|
| 男性 | 50.6% |
| 女性 | 48.8% |
| 職種 | 利用割合 |
|---|---|
| サービス業 | 17.5% |
| 営業職 | 12.2% |
| 医療関連 | 7.9% |
| 販売業 | 7.4% |
| 製造業 | 7.1% |
| IT・技術系 | 6.3% |
| 不動産業 | 5.7% |
| 教員関連 | 5.6% |
| 事務関連 | 5.4% |
| 建築・建設業 | 4.6% |
| 飲食業 | 4.5% |
| 美容関連 | 3.1% |
| 介護関連 | 2.9% |
| 金融・保険業 | 2.8% |
| 運送業 | 2.7% |
| メディア関連 | 2.1% |
| 派遣登録 | 0.7% |
| 公務員 | 0.4% |
| 警備業 | 0.3% |
| 倉庫業 | 0.3% |
| 清掃業 | 0.1% |
| 水商売 | 0.1% |
| その他 | 0.3% |
営業や接客ではコミュニケーションの負担が、介護では体力的な限界が、ITではスキル不足や教育体制の不備が背景にあります。
利用に至った経緯と退職理由
退職代行を利用する新卒者の多くは、社内の人間関係や長時間労働といった環境の問題を抱えています。中には、面接時に聞いていた条件と実際の内容がまったく異なっていたというケースもあります。
退職理由のトップは「人間関係」で、次いで「労働条件の相違」「業務過多」「体調不良」と続きます。とくに「パワハラ」や「無視」などのいじめに類する行為が引き金になることが多く、早期にメンタル不調をきたす人も少なくありません。
| 退職理由 | 割合 |
|---|---|
| 人間関係の悪化 | 31.6% |
| 労働条件の違い | 24.3% |
| 長時間労働 | 18.9% |
| 精神的なストレス | 13.2% |
| 体力的な限界 | 6.4% |
| その他 | 5.6% |
自力での解決が難しいと判断した結果、退職代行という手段を選んだ新卒者が多いことが明確に表れています。
引用元:PRTimes
新卒で退職代行を使うべき状況
新卒社員が退職代行を使うべき状況は、精神的・肉体的に過度な負担を抱えている場合や、会社との直接のやりとりが難しいときです。労働条件の食い違いやパワハラなどの問題があれば、早期に専門サービスへ相談することが適切です。問題を放置すると健康被害やキャリアへの影響につながる恐れがあるため、速やかな判断が求められます。
- 労働条件が契約内容と大きく異なる
- パワハラ・職場いじめがある
- 退職の意思を伝えても拒否される
- 精神的ストレスで出社が困難になっている
- 会社と直接連絡を取るのが怖い、または遮断されている
労働条件が事前説明と異なる
求人票や面接時の説明と、実際の労働条件が著しく異なる場合は、退職代行の利用が正当な判断となります。たとえば、残業代が支払われない、休日が事前より少ない、業務内容が大幅に異なるなど、明らかに契約内容と違う状況は違法性を含んでいる可能性があります。
こうした場合、自力で改善を求めるのは難しいため、退職代行を通じて第三者が介入してもらい、冷静かつスムーズに問題を解消できます。
 LiNee編集部
LiNee編集部新卒という立場では交渉経験も少なく、社内の人間関係や評価を気にして言い出せないケースが多く見られます。
退職代行のなかには、労働条件の不備に関するアドバイスや証拠の整理を支援してくれるサービスも存在します。労働基準監督署への相談よりも迅速に対応できるという利点もあります。
職場でのパワハラや人間関係の問題
上司や先輩社員からのパワハラ、無視やいじめなどの職場トラブルは、早期に対応すべき深刻な問題です。特に新卒社員は相談できる相手が少なく、問題を一人で抱えがちです。精神的な負荷が限界を超える前に、専門サービスの力を借りて離脱する選択が合理的です。
新卒社員が抱えるパワハラ被害には、暴言、長時間労働の強制、私生活への過干渉などが含まれます。こうした行為は労働基準法違反に該当する可能性があります。
 LiNee編集部
LiNee編集部労働基準法違反に該当する内容は、記録を残す(音声・メール)ことで今後の転職活動にも説明材料として活用できます。
退職代行サービスでは、こうした人間関係のトラブルにも対応実績があります。利用にあたっては、過去のやりとりやメモ、メールなどを用意しておくと、よりスムーズに退職を進められます。
退職を拒否される、または連絡手段が絶たれている場合
会社に退職の意思を示しても聞き入れてもらえない、または連絡自体を遮断される状況では、退職代行サービスの利用が有効です。特に中小企業では、退職の自由を認めず、本人に強い圧力をかける事例も報告されています。
実際の現場では、「人手不足だから辞められない」「もう少し頑張れば慣れる」といった言葉で退職を引き延ばすケースも多く見られます。中には、上司が連絡を無視し、退職の申し出をなかったことにする企業も存在します。
退職代行業者を通じて会社に正式な退職通知を送ることで、退職の意思が確実に伝わり、法律に基づいた手続きが進みます。民間の退職代行だけでなく、労働組合運営や弁護士対応のサービスを選べば、より強い効力を持って対応してもらえます。
新卒で退職代行を利用するメリット
新卒社員が退職代行を利用する最大のメリットは、精神的な負担を軽減しながら退職できる点にあります。会社との直接対話が不要になることで、心理的なストレスを避けながら、確実に退職手続きを進めることができます。早期に環境を変えることで、心身の健康を守り、次のキャリアへの準備を前向きに行うことが可能になります。
- 会社と直接やりとりしなくて済む
- 即日で退職の意志を伝えられる
- 精神的ストレスを最小限にできる
- 法的トラブルを防ぎながら安全に辞められる
- 次のキャリアへの準備が早く始められる
会社と連絡を取らずに退職できる安心感
退職代行サービスを利用すれば、上司や人事担当者と顔を合わせる必要なく、第三者を通じて退職の意思を伝えることができます。入社したばかりの新卒社員にとって、退職を申し出ることは非常に大きな心理的ハードルとなります。特に職場での人間関係が悪化している場合や、すでに不信感を抱いている状況では、自ら申し出ることが困難になります。
退職代行を使うことで、本人の精神的な負担を軽くしながら、プロのサポートによってトラブルの発生を未然に防ぐことが可能です。退職の意志がスムーズに伝わることで、退職手続きも早期に進みます。
 LiNee編集部
LiNee編集部連絡の回避は単なる「逃げ」ではなく、健全な判断として受け止められるケースが増えています。新卒者の多くが同様の理由で退職代行を選択しており、もはや一般的な方法として定着しつつあります。
即日対応で心身のダメージを最小限にできる
退職代行サービスの多くは、相談から即日での対応が可能です。これ以上職場に行く必要がないという安心感が得られます。精神的に追い詰められている状況では、翌日の出勤が恐怖に感じるほどの負担になることがあります。
サービスによっては、朝に連絡をすればその日のうちに会社に通知が届き、退職の手続きがすぐに進行します。こうしたスピード感のある対応は、新卒者がこれ以上の苦痛を感じずに済むという意味でも非常に有効です。
出社せずに退職が完了すれば、職場での対面によるトラブルや説得も発生しません。自宅でのやりとりだけで完結することで、安心して次のステップを考えられるようになります。
法律の知識がなくてもスムーズに退職できる
退職手続きには法律的な要素が多く含まれますが、退職代行を利用すれば専門知識がなくても適切に対応してもらえます。特に弁護士や労働組合が運営するサービスを選べば、法的トラブルにも備えた万全の対応が受けられます。
未払いの給与や有給休暇の消化、私物の返却など、退職時には細かな問題が発生することがあります。自分一人でこれらをすべて対応するのは難しく、不安になるケースも多いです。
その点、退職代行は本人の代理人として企業とやりとりを行い、円滑に問題解決へと導いてくれます。トラブルが予想される場合には、弁護士による法的文書の送付なども可能です。
新卒で退職代行を利用するデメリット
退職代行は便利な手段ですが、すべてのケースで最良の方法とは限りません。利用には費用や転職活動への影響、周囲の理解を得にくいといったデメリットが伴う可能性があります。特に新卒という立場では、将来のキャリアや信用にも関わる要素があるため、慎重な判断が求められます。
- 費用が発生する
- 転職時に理由を聞かれることがある
- 自己解決能力が低いと見なされる場合がある
- 家族や周囲の理解を得にくいことがある
- 退職理由を伝える機会が本人にない
費用が発生し、金銭的負担になる
退職代行サービスは無料ではなく、2万〜5万円程度の費用が必要になります。新卒の初任給や生活費から捻出するには大きな負担になる場合があります。とくに一人暮らしや貯金が少ない人にとっては、経済的に悩む要因となります。
また、弁護士型サービスを利用する場合はさらに高額になり、依頼内容によっては追加料金が発生することもあります。返金保証がある業者もありますが、条件が厳しい場合が多いため注意が必要です。
サービスを選ぶ際には、料金体系が明確であるか、後払いに対応しているかなども確認することが大切です。
転職活動で不利になる可能性がある
退職代行を使ったことが次の転職に悪影響を及ぼす可能性もあります。面接の場面で「なぜ退職代行を使ったのか」と聞かれることがあり、納得のいく理由を説明できなければ印象が悪くなることがあります。
採用担当者は自己解決能力やコミュニケーション能力を重視する傾向があるため、自ら退職の意思を伝えずに他者に任せたことをマイナスに受け取る場合もあります。
ただし、退職理由や状況を冷静に説明できれば、むしろ合理的な判断として評価される場合もあります。転職エージェントのサポートを受けながら、ポジティブに伝える準備をすることが効果的です。
家族や周囲から理解を得にくい場合がある
退職代行の利用に対して、世代や価値観の違いから否定的な意見を持つ人もいます。とくに親世代は「自分で言わないとだめだ」「甘えている」と考える傾向が強く、理解が得られないことがあります。
結果として、退職後に家族との関係が悪化したり、身近な人から責められたりするケースも存在します。自分の心と身体を守るための判断であっても、正しく説明しないと誤解を招く恐れがあります。
周囲の理解を得るためには、事実や背景を丁寧に伝えることが大切です。退職後に精神的に回復した姿を見せることで、結果として信頼を取り戻すことにもつながります。
新卒で退職代行を利用した人の体験談
実際に退職代行を利用した新卒社員の体験談には、共通して「精神的に救われた」「自分では言い出せなかったので助かった」という声が多く見られます。不安や後悔を感じる人もいますが、最終的には「行動して良かった」と前向きな感想で締めくくられることが多いです。
- 上司に強く引き止められそうだったが、退職できた
- 初日で辞めたが、罪悪感より安心感が大きかった
- 家族の反対があったが、結果的に支えてもらえた
- 精神的に限界だったが救われたと感じた
- 退職後、第二新卒枠で転職に成功した
 LiNee編集部
LiNee編集部以下は、2024年から2025年にかけて退職代行を利用した新卒社員の体験談です。職種や退職時期、サービス利用の背景などに個人差がありますが、それぞれの事情と心情がわかる内容になっています。
営業職/男性/東京都/2024年4月入社→5月退職(退職代行ガーディアン利用)
入社から1週間で営業先への飛び込み訪問を強要され、精神的に追い詰められていきました。相談できる上司もおらず、夜眠れない日が続いたため退職代行に相談しました。翌日には会社に退職の連絡を入れてくれて、無事に辞めることができました。あのときの判断がなければ、今も消耗し続けていたと思います。
建設業/男性/愛知県/2024年4月入社→5月退職(退職代行ガーディアン利用)
現場での肉体労働が想像以上にきつく、先輩からの暴言にも悩まされていました。親には相談できず、ひとりで抱え込んでいましたが、退職代行にメールしたらすぐに対応してくれて助かりました。もう一度やり直そうと思えました。
介護職/女性/大阪府/2024年4月入社→6月退職(退職代行OITOMA利用)
配属された施設での人間関係が悪く、指導担当者からの嫌がらせや陰口に苦しんでいました。退職の意志を伝えても「甘えるな」と拒否され、退職代行を使う決断をしました。料金は少しかかりましたが、会社からの連絡も一切なくスムーズに辞められて心からホッとしました。
保育士/女性/千葉県/2024年4月入社→5月退職(退職代行OITOMA利用)
保育園での職場いじめに耐えきれず、出勤ができなくなりました。園長に何度相談しても無視され、心が折れてしまいました。退職代行を使ったあとは、会社に行かずに退職できて安心しました。今は自分に合う仕事を探しています。
販売職/女性/福岡県/2024年4月入社→4月末退職(退職代行モームリ利用)
初出勤の日から店長の対応に違和感を感じていました。「新人は黙って言うことを聞け」と高圧的な態度で、2週間で限界がきました。退職代行を使うのは恥ずかしいと思っていたけれど、実際に相談してみたらとても親切で安心できました。家族も最初は驚いていましたが、今は応援してくれています。
地方公務員内定辞退/男性/広島県/2025年度内定者(退職代行モームリ利用)
入庁前から不安があり、ネットで情報を集めているうちに退職代行の存在を知りました。内定辞退でも対応してくれるサービスがあることを知り、早めに決断できました。大学の友人には驚かれましたが、後悔はありません。
IT企業/男性/埼玉県/2024年4月入社→7月退職(退職代行Jobs利用)
入社直後から残業が続き、業務量が異常に多かったです。しかも「新人は残って覚えろ」という風潮があり、体調を崩して通院するようになりました。自分で退職を申し出る勇気がなかったので退職代行に頼みました。結果的に、通院をやめてリモート勤務できる企業に転職できたので満足しています。
飲食業/女性/京都府/2024年4月入社→5月末退職(退職代行Jobs利用)
週6勤務で休憩時間も取れず、心身ともに限界でした。相談窓口もなかったため、退職代行を利用しました。やめた当日は気まずさがありましたが、翌日から気持ちがすっきりしました。転職活動も順調に進んでいます。
事務職/女性/神奈川県/2024年4月入社→5月中旬退職(退職代行みやび利用)
事務職なのに毎日電話営業を強要され、聞いていた仕事内容と違いすぎて驚きました。先輩も全く教えてくれず、孤独な環境で泣きながら帰った日もありました。退職代行みやびは相談から対応までとても丁寧で、心が落ち着きました。今は派遣社員として無理なく働いています。
製造業/男性/北海道/2024年4月入社→6月退職(退職代行みやび利用)
工場での業務が予想以上に過酷で、入社後に聞かされていなかった夜勤も追加されました。これ以上働き続ける自信がなく、退職代行に連絡しました。手続きは早く、対応も丁寧でした。体調が回復した今、別の業種を目指しています。
新卒が退職代行で辞めるまでの流れ
新卒が退職代行で会社を辞めるには、手順を踏んで計画的に進めることが大切です。退職代行は申し込みから退職完了までの流れが明確に決まっており、ほとんどのケースでトラブルなく退職できます。自分で直接伝えづらい場合でも、専門のサービスを利用することでスムーズな退職が可能になります。
- 相談・申し込みから退職までは最短で即日も可能
- 希望条件や退職理由は事前に伝える必要がある
- サービスにより対応の丁寧さや流れに違いがある
相談・申し込みから退職完了までのステップ
退職代行サービスを利用する際は、まず相談から始まります。無料相談を受け付けているサービスが多く、LINEや電話、メールなどで気軽に問い合わせできます。相談後に正式な申し込みをすると、担当者とのやり取りが始まります。この段階で希望の退職日や連絡を避けたい人などの条件を詳しく伝えます。
申し込みが完了すると、退職代行業者が勤務先に連絡し、退職の意思を代理で伝えてくれます。その後、退職届の郵送や貸与物の返却、健康保険証の返送など、退職手続きに必要な書類を準備します。退職が完了するまで、進行状況は随時報告されるため、安心して任せることができます。
費用支払い・希望条件の伝達方法
退職代行の費用は、前払い・後払い・分割払いなどサービスによって異なります。一般的には2万円~5万円程度で、弁護士が対応する場合は5万円以上になることもあります。
 LiNee編集部
LiNee編集部支払い方法はクレジットカード・銀行振込・電子決済などがあり、即日対応のためにはすぐに決済できる手段が必要です。
希望条件の伝達は、電話やLINE、専用フォームなどで行います。伝えるべき内容には、退職希望日・有給の消化希望・退職理由・会社とのやり取りの有無などがあります。情報を正確に伝えることで、トラブルや誤解を防ぎ、スムーズに退職できます。
退職手続きが完了するまでの平均期間と対応内容
退職代行を利用した場合の平均的な退職完了までの期間は、2日~1週間程度です。即日退職が可能なサービスもありますが、会社側の対応によっては多少時間がかかることもあります。
退職代行業者の対応内容には、以下のようなものがあります。
- 勤務先への退職連絡の代行
- 有給休暇の取得申請代行
- 退職届の書き方のアドバイス
- 貸与物の返却や書類のやり取りの指導
- 家族や本人への連絡の制限サポート
中でも弁護士事務所が運営する退職代行サービスでは、会社との法的交渉が可能であり、有給取得や残業代請求などの対応範囲が広いです。労働組合運営のサービスも、交渉が合法的に認められているため、より安心して利用できます。
退職代行選びに失敗しないためのポイント
退職代行サービスを選ぶ際は、信頼性や対応範囲、料金体系などを事前にしっかり確認することが大切です。サービスごとに運営主体やサポート内容が異なるため、自分の希望や状況に合ったものを選ばないと後悔する可能性があります。選び方を間違えると、退職手続きがスムーズに進まなかったり、追加費用が発生したりすることもあります。
- 弁護士や労働組合が運営しているか確認する
- 料金が明確で後払い・返金保証の有無もチェックする
- サポートの範囲や対応スピード、評判を比較する
弁護士や労働組合運営かどうかの確認
退職代行サービスを選ぶ上で最も大切なのは、誰が運営しているかを確認することです。弁護士が運営しているサービスは、法律に関する交渉も代行できるため、有給休暇や未払い賃金の請求、損害賠償への対応も可能です。
 LiNee編集部
LiNee編集部一般企業が運営するサービスは「伝えるだけ」が基本で、法的交渉は行えません。
労働組合が運営する退職代行サービスは、団体交渉権を持つため、会社に対して一定の交渉が可能です。モームリやガーディアンのように、労働組合と連携しているサービスであれば、安心して依頼できます。自分の退職理由や状況に応じて、交渉力が必要かどうかを基準に選ぶことが大切です。
料金体系、後払い・返金保証の有無
退職代行の料金はサービスによって異なり、料金体系を理解しておかないとトラブルの原因になります。相場は2万〜3万円程度ですが、弁護士対応のサービスでは5万円以上になることもあります。「一律料金制」「オプション追加型」「後払い可」など、支払い方法や料金プランの仕組みも確認が必要です。
後払いに対応しているサービスは、料金を先に支払えない人にとって利用しやすいです。退職できなかった場合に返金してくれる保証制度があるサービスもあります。サービス利用前に、契約内容や料金の返金条件などを細かくチェックしておくことで、安心して依頼できます。
サポート内容・評判・対応スピードなどのチェック方法
サポート体制や対応の丁寧さも、サービス選びで失敗しないための重要な要素です。24時間対応や即日対応の有無、LINE・メール・電話などの連絡手段、対応スピードに差があります。中には、深夜帯でも即返信してくれる対応力の高いサービスも存在します。
口コミや評判を確認する際は、SNSや口コミサイト、Googleレビューなどを活用します。「連絡が遅い」「返答が曖昧だった」などの意見が多い場合、そのサービスは避けた方が良いです。利用者の声を事前に確認して、信頼できると判断できるサービスに依頼することが安心につながります。
新卒におすすめの退職代行サービス比較
新卒が安心して利用できる退職代行サービスを選ぶには、料金、対応スピード、サポート体制などを比較することが大切です。実績や利用者の評判も信頼性を判断する基準になるため、複数のサービスを比較して自分に合ったものを選ぶ必要があります。法的対応が可能かどうかや、相談しやすさにも差があります。
- 新卒向けに実績があるサービスを選ぶと安心できる
- LINE対応や即日対応などスピード感も重視されている
- 法的交渉が必要な場合は弁護士対応のサービスが適している
退職代行Jobs

| 運営タイプ | 労働組合 |
|---|---|
| 料金 | 27,000円(税込)~ |
| 支払タイミング | 前払い 後払い |
| 追加料金 | なし |
退職代行Jobsは労働組合と連携し、法的交渉にも対応している信頼性の高いサービスです。運営元は株式会社アレス、労働組合「合同労働組合ユニオンジャパン」が代行を担当しています。相談はLINEで可能で、深夜や土日祝でも対応してくれます。
料金は一律27,000円(税込)で、追加費用がかかることはありません。有給消化サポートや退職届のテンプレート提供などもあり、サービス内容は総合的に充実しています。万が一退職できなかった場合は全額返金保証も用意されています。
退職代行Jobsの基本情報
| サービス名 | 退職代行Jobs |
|---|---|
| 運営会社名 | 株式会社アレス (合同労働組合ユニオンジャパン) |
| 料金 | 27,000円(税込) +労働組合費2,000円 |
| 返金保証 | あり |
| 後払い | 可能 |
| 支払方法 | 銀行振込 クレジットカード コンビニ決済 現金翌月払い |
| 退職成功率 | 非公開 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| サービス内容 | 退職の意思を 会社に伝達 |
| 特徴 | 労働組合と提携し 会社と交渉可能 |
| メリット | 即日退職が可能で 引き止められない |
| 監修者 | 弁護士 西前啓子 |
| 公式サイト | https://jobs1.jp/ |
退職代行ガーディアン

| 運営タイプ | 労働組合 |
|---|---|
| 料金 | 24,800円(税込) |
| 支払タイミング | 前払い |
| 追加料金 | なし |
退職代行ガーディアンは東京労働経済組合が運営しており、団体交渉権を活かした交渉力が特徴です。法律に基づいた確実な代行を求める新卒におすすめです。365日24時間対応で、即日退職にも柔軟に対応しています。
料金は24,800円(税込)で、明確な一律料金となっており、追加費用は発生しません。LINEや電話での相談が可能で、無料の事前相談も対応しています。有給取得の交渉実績も多く、過去にトラブルが起きた事例が少ない点も評価されています。
退職代行ガーディアンの基本情報
| サービス名 | 退職代行ガーディアン |
|---|---|
| 運営会社名 | 合同労働組合ガーディアン |
| 料金 | 一律24,800円(税込) |
| 返金保証 | 記載なし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込 クレジットカード(VISA、Mastercard) |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 退職の意思を会社へ伝達 有給消化や未払い賃金の交渉 即日対応可能 |
| 特徴 | 労働組合運営で交渉力あり 追加料金なしの明確な料金体系 24時間365日対応 |
| メリット | 低価格で高品質なサービス 即日退職が可能 |
| 監修者 | 記載なし |
| 公式サイト | https://taisyokudaiko.jp/ |
退職代行OITOMA

| 運営タイプ | 労働組合 |
|---|---|
| 料金 | 24,000円(税込) |
| 支払タイミング | 前払い 後払い |
| 追加料金 | なし |
退職代行OITOMAはコストパフォーマンスの高さと即日退職の対応スピードで人気です。運営元は株式会社H4で、労働組合「労働組合運営日本通信ユニオン」と連携して交渉に対応します。LINEでのやりとりが中心となっており、返信もスムーズです。
料金は24,000円(税込)で後払いにも対応しています。また、退職届の作成サポートや書類の郵送案内もあり、新卒の利用者からも評価が高いです。サポート対応の柔軟性が高く、離職後のアドバイスも充実しています。
退職代行OITOMAの基本情報
| サービス名 | 退職代行 OITOMA(オイトマ) |
|---|---|
| 運営会社名 | 株式会社H4 |
| 料金 | 24,000円(税込) |
| 返金保証 | 退職できなかった場合、全額返金保証 |
| 後払い | 可能(手数料5,000円、最長1ヶ月以内の支払い) |
| 支払方法 | 現金、クレジットカード |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 退職手続きの代行 会社への連絡代行 退職届の作成サポート |
| 特徴 | 労働組合と提携 24時間365日対応 追加料金なし |
| メリット | 即日退職が可能 全額返金保証で安心 |
| 監修者 | 行政書士東京中央法務オフィス |
| 公式サイト | https://o-itoma.jp/ |
退職代行みやび

| 運営タイプ | 弁護士法人 |
|---|---|
| 料金 | 正社員・契約社員:27,500円(税込) 公務員:55,000円(税込) 自衛隊・業務委託・会社役員:77,000円(税込) |
| 支払タイミング | 記載なし |
| 追加料金 | なし |
退職代行みやびは弁護士が直接対応する退職代行サービスです。法律事務所が運営しており、未払い残業代の請求などにも対応可能です。新卒でトラブルがある場合や確実に法的に進めたい人に向いています。
料金は27,500円(税込)~で、交渉力と対応の丁寧さは抜群です。会社からの損害賠償請求リスクにも対応しており、安心して任せられます。弁護士対応のため、依頼者の代理として企業と直接やりとりできる点が他と異なります。
退職代行みやびの基本情報
| サービス名 | 退職代行 弁護士法人みやび |
|---|---|
| 運営会社名 | 弁護士法人みやび |
| 料金 | 正社員・契約社員:27,500円(税込) 公務員:55,000円(税込) 自衛隊・業務委託・会社役員:77,000円(税込) |
| 返金保証 | 記載なし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込 クレジットカード |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 弁護士が直接退職手続きを代行 会社への連絡 退職届の提出 未払い給与・有給休暇の請求 退職後のサポート |
| 特徴 | 法的知識に基づく 適切な対応 |
| メリット | 有給消化や未払い給与の 交渉も可能 |
| 監修者 | 弁護士法人みやび |
| 公式サイト | https://taishoku-service.com/ |
人気サービスの料金・対応力比較一覧表
| サービス名 | 運営主体 | 料金(税込) | 法的交渉対応 | 即日対応 | 返金保証 | 連絡手段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退職代行Jobs | 労働組合連携 | 29,000円 | 労働組合対応 | 対応可能 | あり | LINE 電話 |
| 退職代行ガーディアン | 東京労働経済組合 | 24,800円 | 労働組合対応 | 対応可能 | なし | LINE 電話 |
| 退職代行OITOMA | 労働組合連携 | 24,000円 | 労働組合対応 | 対応可能 | あり | LINE中心 |
| 退職代行みやび | 弁護士事務所 | 27,500円 | 弁護士対応 | 対応可能 | 要確認 | メール 電話等 |
サービスを比較することで、費用だけでなく対応の違いや安心できるポイントが見えてきます。
自分の状況に最も適した退職代行を選ぶことが、スムーズな退職とその後の再出発につながります。
退職代行後のキャリアと転職活動の進め方
退職代行を使って退職した後でも、キャリアを立て直すことは十分可能です。新卒での早期退職は珍しくなく、再出発の準備をしっかり行えば、第二新卒として有利な転職も可能です。自己分析やスキルの整理、転職市場の理解が次の一歩につながります。
- 第二新卒市場ではポテンシャル採用が主流
- 退職理由は前向きに説明することが大切
- 自己分析とスキルの見直しが転職成功のカギになる
第二新卒市場の現状と採用されやすい業界
第二新卒は新卒入社後おおむね3年以内の転職希望者を指し、多くの企業が柔軟に採用しています。特に人材不足が続く業界では、社会人経験の浅い第二新卒の需要が高まっています。「社会人としての基礎があるが、成長段階にある若手」として、教育コストを抑えつつ長期的に育成できる人材として評価されます。
採用が活発な業界には、IT業界、営業職、接客・販売、介護・医療などがあります。これらの分野では、未経験者歓迎の求人が多く、ポテンシャル重視で選考が行われる傾向があります。業界ごとの特徴を把握して、自分の適性に合った業種を選ぶことで再スタートしやすくなります。
早期退職の理由を前向きに伝える方法
面接での退職理由の伝え方は、転職成功に直結する重要なポイントです。ネガティブな理由がある場合でも、そのまま伝えるのではなく、自分なりに学んだことや今後に活かしたい点を中心に話すと印象が良くなります。
 LiNee編集部
LiNee編集部例えば、「実際の業務が希望していた内容と異なっていたが、その経験で自己理解が深まり、本当にやりたい分野が明確になった」といった表現が有効です。
また、「働く上で大切にしたい価値観に気づいた」といった内容にすると、前向きな姿勢が伝わります。避けるべきなのは、「人間関係が最悪だった」「ブラック企業だった」といった感情的な表現です。
自己分析・スキル整理と再出発への準備
退職後は一度立ち止まり、自分の強みや適性を整理する時間を設けることが大切です。何が得意で、何に興味があり、どんな働き方を望んでいるのかを明確にすると、転職活動がスムーズに進みます。
自己分析にはキャリアアドバイザーや転職エージェントの支援を活用すると、客観的な視点で強みを見つけやすくなります。履歴書や職務経歴書を作成する際も、自分のスキルや経験を具体的に言語化する練習になります。前職で経験した業務の中から、他業界でも応用できるスキルを抽出することが成功の鍵です。
転職活動の準備が整ったら、求人サイトやエージェントを活用して情報を収集し、無理のないペースで応募を進めていきます。「次は長く働ける職場を見つけたい」という気持ちを持って、焦らず丁寧に進めることが再スタートへの第一歩になります。
新卒の退職代行に関するよくある質問(FAQ)
- 新卒でも退職代行を利用して本当に辞められますか?
-
新卒でも退職代行を利用して辞めることは可能です。労働者には「退職の自由」が法律で認められており、入社直後であっても自分の意思で退職できます。退職代行は、その意思を会社に伝える手段として機能します。会社が退職を拒否することはできず、代行業者を通じて退職手続きを進めることができます。
- 入社して1週間以内でも退職代行は使えますか?
-
入社して数日でも退職代行を利用できます。実際に、研修中や初出勤日のみ勤務したケースでも、退職代行を使って退職した事例があります。早すぎる退職に戸惑いを感じるかもしれませんが、労働者が精神的・身体的に負担を感じている場合は早期の判断が有効です。
- 会社から退職を拒否された場合でも辞められますか?
-
会社に退職を拒否する権利はありません。正社員・契約社員を問わず、退職の申し出から2週間経過すれば、法律上の効力が生じます。会社が引き留めたり、退職届を受理しなくても、退職代行サービスがその意思を伝えることで手続きは進みます。
- 新卒が退職代行を使うと社会的に悪く見られませんか?
-
社会的に批判的な意見も一部にありますが、近年は理解が広がっています。特に若手の労働環境やメンタルヘルスが注目されており、自分を守る手段として退職代行を選ぶことは合理的な判断です。企業側も退職代行の対応に慣れてきており、退職した後に悪影響が及ぶことは少なくなっています。
- 親や家族に連絡されることはありますか?
-
原則として、退職代行業者が会社に家族への連絡を避けるよう伝えてくれます。ただし、緊急連絡先として家族の情報が提出されている場合、会社が独自に連絡してしまう可能性はゼロではありません。心配な場合は、事前に業者に伝えておくことで対策が可能です。
- 新卒で退職代行を使うと転職活動に不利になりますか?
-
退職代行を使ったこと自体は転職に不利にはなりません。採用担当者が重視するのは、退職理由と次のキャリアに対する前向きな姿勢です。理由を丁寧に説明し、自分なりの反省点や学びを伝えることで、評価が下がることは避けられます。
- 退職代行に相談するだけでも料金がかかりますか?
-
多くの退職代行サービスは、相談だけなら無料です。LINEやメールでの問い合わせが中心で、何度質問しても費用が発生しないケースが多いです。正式な依頼を行う前に、気になる点は相談して確認しておくと安心です。
- 新卒で退職代行を使うメリットは何ですか?
-
自分で退職を伝えるストレスを回避できる点が最大のメリットです。上司への連絡が怖い、職場に行くのがつらいといったケースでは精神的な負担を大きく軽減できます。また、有給の取得や書類の郵送指導なども受けられるため、退職に必要な作業を効率的に進めることができます。
- 新卒でも即日で辞められますか?
-
会社の了承が得られれば即日退職は可能です。ただし、法律上は退職の申し出から2週間後に退職の効力が発生するため、即日退職を希望する場合は、代行業者が会社と調整する必要があります。有給休暇の消化や欠勤扱いで対応するケースもあります。
- 退職代行の料金はどれくらいかかりますか?
-
料金は2万円〜5万円程度が相場です。労働組合が運営するサービスは比較的安価で、弁護士が対応する場合は費用が高くなります。中には後払い対応や全額返金保証付きのサービスもあるため、自分の状況に合った業者を選ぶことが大切です。
まとめ
新卒で退職代行を使うことに迷いがある人は少なくありません。不安や葛藤を抱えながらも、退職という大きな決断をすることに勇気が必要です。精神的な限界を感じる前に、自分を守る手段として退職代行を選ぶことは間違いではありません。
退職代行の仕組みや流れ、選び方、そして退職後のキャリア形成まで、この記事では新卒に特化した情報を体系的に解説してきました。安心して前に進むためには、正しい知識と判断が欠かせません。
- 新卒でも法律上は自由に退職できる
- 入社直後や研修中でも代行は利用可能
- 退職理由に応じたサービス選びが大切
- 退職後の転職では前向きな姿勢が評価される
- 自己分析と情報収集が再出発の土台になる
新卒で退職代行を使うことは「逃げ」ではなく、現実的な選択肢のひとつです。自らの限界を見極め、適切なタイミングで環境を変えることが、長期的なキャリア形成においても有益です。退職後の進路に不安を感じる場合でも、第二新卒という市場では多くのチャンスがあります。
自分に合った働き方を見つけるための一歩として、退職代行の正しい知識と活用法を理解し、後悔のない選択をしてください。