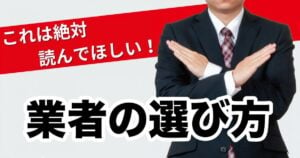「ボーナス前に退職したいけど、もらえるか不安…」そんな悩みを抱えているあなた、実は諦める必要はありません!
退職代行を使っても、ボーナスを受け取れる可能性は大いにあります。就業規則や退職のタイミングによっては、退職後も満額ゲットできるケースも珍しくありません。
「でも、退職代行って本当に大丈夫なの?」「手続きが複雑そう…」そんな心配もご無用です。
ボーナス受け取りにおすすめの退職代行サービスはこちら(当記事下)
退職代行でもボーナスは受け取るための知識
退職代行を利用してもボーナスを受け取ることは可能です。法律上、退職代行を使うこと自体がボーナス支給の妨げになることはありません。ただし、会社側が定めた就業規則や支給要件を満たしていないと、支給されないケースもあります。正しい知識と準備を持つことが、損を防ぐ第一歩になります。
- 退職代行を使ってもボーナス支給に影響はない
- 支給対象かどうかは就業規則で決まる
- 在籍要件と査定期間の確認が必要
- 支給後に退職するタイミングが安全
退職代行を使ってもボーナスは支給されるのか
退職代行を利用して退職したとしても、ボーナスが支給されるかどうかは在籍状況と会社の規定に左右されます。退職代行を使うことで評価が下がったり、待遇が不利になったりするという心配はありますが、支給要件を満たしていればボーナスは通常どおり受け取れます。
 LiNee編集部
LiNee編集部退職代行を使ったからといって、ボーナスが自動的に減額されたり不支給になったりすることはありません。
多くの退職代行事例でも、支給日まで在籍していた場合、満額受け取れているケースが多くあります。ただし、ボーナスの支給は会社の裁量に委ねられる部分もあり、必ず支払われるわけではありません。そのため、退職日と支給日のタイミングが極めて重要になります。
ボーナスに法的な支払い義務はある?
ボーナスは法律上、支給義務が明確に定められているものではありません。労働基準法にはボーナスについての直接的な規定がないため、会社ごとの就業規則や雇用契約書の内容に従って判断されます。
ただし、支給が恒常的であり、労働者にとって当然の権利とみなされるような状況では、「賃金の後払い」として扱われ、支給義務が認められる場合もあります。
 LiNee編集部
LiNee編集部ボーナスの支給に関する過去の実績や社内文書の確認は非常に重要です。
ボーナスが「一時金」として扱われる場合は、会社の業績や上司の評価などをもとに支給額が決まり、支給されないこともあります。退職時の状況によって判断されるため、個別対応が求められます。
ボーナスの支給は会社の裁量に委ねられる
ボーナスの支給条件や額は、基本的に会社の自由裁量に任されています。多くの企業では、就業規則に「会社の業績や人事評価に基づいて支給する」といった記載があります。このため、退職代行を使った場合、業績評価が十分にされていない、あるいは退職予定者であることから、評価が低くなる可能性があります。
また、査定期間の途中で退職の意思を示していると、その時点でボーナス支給対象外と判断される場合もあります。退職意向を伝えるタイミングや、査定対象期間の終了後まで在籍しているかどうかが、支給の可否に影響を与えます。
評価や業績が基準となっている企業では、本人の努力だけでは調整が難しいこともあります。退職を決めた時点で、就業規則をしっかり確認し、退職代行を利用する前にタイミングを見極めることが損をしないための鍵になります。
ボーナスの支給条件と就業規則のチェックポイント
ボーナスを確実に受け取るためには、会社が定めた支給条件と就業規則の内容を正しく理解しておくことが必要です。支給基準は企業ごとに異なり、在籍要件や査定期間、業績連動の有無などが支給可否を左右します。就業規則や雇用契約書に目を通すことが支給されるかどうかの判断材料になります。
- 支給条件は会社ごとに違う
- 就業規則と雇用契約書の記載が基準になる
- 査定期間の終わりと退職日を照らし合わせる
- 在籍要件をクリアしているか確認する
ボーナス支給の在籍要件とは
多くの会社では、ボーナスを受け取るために「支給日に在籍していること」が条件とされています。この「在籍要件」が就業規則に明記されていれば、たとえ査定対象期間中に働いていても、支給日を迎える前に退職した場合はボーナスが支払われないことがあります。
在籍要件があるかどうかは、就業規則または雇用契約書で確認できます。記載がない場合は慣習や過去の支給実績が基準になりますが、明文化されている場合はそちらが優先されます。
 LiNee編集部
LiNee編集部在籍要件を満たしているかどうかは、支給日まで会社に籍があるかで判断されるため、退職日を決める際には非常に大きな判断材料となります。
特に退職代行を利用する場合は、手続きの都合で予定よりも早く退職処理が進む可能性があるため、事前に代行業者としっかりスケジュールを調整しておくことが欠かせません。
査定期間と支給タイミングの関係
ボーナスの金額や支給対象かどうかを決める上で「査定期間」が存在します。この期間内の勤務実績や勤務態度、会社の業績などをもとに評価が行われ、その評価をもとに支給額が決定されます。
査定期間は通常、支給日の数か月前から半年ほど前の一定期間が設定されています。たとえば夏のボーナスであれば、前年の冬から春にかけての勤務状況が対象になるケースがあります。
 LiNee編集部
LiNee編集部査定期間内にすでに退職の意向を示していた場合、評価が下がる可能性があります。
また、退職意向を表明したタイミングが査定期間中であると「意欲がない」と見なされることもあり、結果として支給額が減ることもあります。退職日を決定する際は、査定期間の終了とボーナス支給日の関係を確認することで、損を防ぐ判断がしやすくなります。
雇用契約書・就業規則の確認手順
就業規則や雇用契約書は、ボーナス支給の条件が明文化されている最も信頼性のある情報源です。退職のタイミングを検討する前に、必ず内容を確認しておくことが大切です。
- 現在の雇用契約書に「賞与」「ボーナス」「一時金」といった文言が記載されているかを確認
- 会社の就業規則を社内ポータルや人事部に確認
 LiNee編集部
LiNee編集部就業規則に「賞与は業績および勤務成績を総合的に勘案し、会社が決定する」などの文言があれば、支給の判断が会社の裁量であることを意味します。
在籍要件や査定期間、支給日についても詳細が書かれていることが多く、それらをもとに退職日を調整することで、損を回避することができます。自分で確認できない場合は、退職代行業者に就業規則の確認を依頼することも可能です。弁護士対応の代行サービスであれば、交渉や確認もスムーズに進むことがあります。
退職代行利用時に発生する可能性のあるトラブル
退職代行を使う場合でも、ボーナスに関連したトラブルが発生する可能性があります。特に多いのが、支給予定だったボーナスの減額や不支給、すでに支給されたボーナスの返還請求です。トラブルを回避するためには、退職代行に依頼する前に就業規則や支給条件を確認し、事前準備を万全に整えておくことが必要です。
- 支給済みのボーナスを返還請求されることがある
- 支給予定だったボーナスが減額または支給されない場合がある
- 査定期間や退職のタイミングによって支給が左右される
- 会社の就業規則に基づいた判断が優先される
退職後にボーナス返還を求められる
ボーナスを受け取ったあとに会社から返還を求められるケースがあります。とくに退職のタイミングが支給直後であった場合、「不誠実だ」と見なされて返還を求められることがあります。ただし、法律上は原則としてボーナスの返還義務はありません。
労働基準法第16条には「賠償予定の禁止」が定められており、労働者に損害賠償や違約金を課すことは禁止されています。このため、会社が一方的に返還を命じても、法的には応じる必要はありません。
(賠償予定の禁止)
労働基準法 | e-Gov 法令検索
第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
トラブルを避けるためには、退職日と支給日のバランスを考え、できるだけ時間を空けるなどの配慮が効果的です。
支給予定のボーナスが減額・不支給になる
ボーナスが支給される予定だったにもかかわらず、退職を理由に減額または不支給になるケースがあります。この理由の多くは、会社側が「支給日には在籍していない」「退職の意向が査定期間中に表明された」といった事情を理由に、支給対象から外すという判断をしていることにあります。
会社の就業規則に「支給日に在籍していること」と明記されている場合、在籍していない時点で支給対象外とされても違法とはいえません。
 LiNee編集部
LiNee編集部「評価に基づいて支給額を決定する」となっている企業では、退職の意思表示そのものがマイナス評価につながる可能性もあります。
不支給の判断がされた場合でも、会社に説明を求めたり、就業規則や過去の支給実績を確認することで、交渉の余地が生まれることもあります。弁護士対応の退職代行であれば、こうした交渉も代理で行ってもらえる場合があります。
ボーナス受け取りにおすすめの退職代行サービスはこちら(当記事下)
トラブルを未然に防ぐための準備不足
多くのトラブルは、退職代行を利用する前の準備不足によって引き起こされます。就業規則や支給条件を確認せずに依頼を進めてしまい、後から「実は在籍要件があった」「査定期間がまだ終わっていなかった」と気付くことで、トラブルが発生します。
- 雇用契約書と就業規則をチェックし、ボーナスの支給条件を明確する。
- 支給日を把握し、退職日がその後になるように調整する。
- 支給額に関する証拠として、給与明細や社内メールを保存しておく。
実際にトラブルが発生してしまった場合は、弁護士や労働組合の支援を受けることで、対応がスムーズになります。特にボーナスに関する金銭トラブルは、法律的な根拠に基づいて対応することが有効です。
ボーナスを受け取ってから辞めるためのベストなタイミング
ボーナスを確実に受け取ってから退職するには、「支給日後に在籍していること」がもっとも確実な方法です。就業規則で定められている在籍要件を満たし、かつ査定への影響を回避するためには、退職の申し出や退職代行の依頼のタイミングに注意が必要です。
- 支給日を過ぎるまで退職しない
- 査定期間終了後に退職意向を伝える
- 在籍要件と就業規則を事前に確認しておく
- 退職代行と日程調整を行う
退職を伝えるのはいつがベストか
退職の意思を伝えるタイミングは、ボーナス支給後が最も安全です。多くの会社では「支給日に在籍していること」が支給条件として明記されていますが、支給日前に退職届を提出すると、評価に影響を与える可能性があります。
退職の意思表示が査定期間中に行われた場合、「勤務意欲が低い」と判断され、ボーナスの金額が減額されるケースもあります。最悪の場合、「辞めるとわかっている社員には支給しない」という判断をされることもあります。
退職を伝えるベストなタイミングは、査定が確定した後かつ支給日を過ぎた後です。就業規則に在籍要件がある場合は、支給日に在籍していればその後すぐに退職を申し出ても問題ありません。
ボーナス支給日を確実に把握する方法
ボーナス支給日は会社によって異なるため、正確に確認しておく必要があります。支給日を把握するには、過去の給与明細や社内のお知らせ、雇用契約書、就業規則などの文書を参照します。
過去の支給履歴を見れば、毎年の支給パターンがわかることが多くあります。
退職代行サービスを利用する場合も、事前に支給日を伝えておくことで、退職日との調整がスムーズになります。事前確認を怠ると、在籍要件を満たせずに支給されない事態が起こるため、念入りな確認が必要です。
ボーナス支給後から退職完了までの流れ
ボーナス支給日を過ぎてから退職を完了させるまでには、いくつかの段階を踏むことが安全です。まず支給を確認し、そのうえで退職日を確定させます。次に退職代行業者とスケジュールを共有し、退職の意思表示を実行します。
 LiNee編集部
LiNee編集部退職代行サービスによっては、本人がボーナス支給後に退職意志を表明するという日程を踏まえて、スムーズな退職手続きを支援してくれます。
退職の連絡は即日であっても、会社側との調整が必要なケースもあるため、計画的に進めることが求められます。
退職日が支給日と近すぎる場合、誤って支給前に退職扱いとなるリスクもあるため、少なくとも支給日から数日程度は空けたほうが安全です。こうした流れを把握しておくことで、退職時の混乱や支給漏れを防ぐことができます。
ボーナス受け取りにおすすめの退職代行サービスはこちら(当記事下)
法律的に問題ない?退職とボーナスの境界線
退職とボーナスの関係には、法律的な問題が発生する可能性がありますが、正しく理解すれば不当な対応を受けずに済みます。労働基準法をはじめとした法律では、ボーナスの支給義務や返還請求に対して一定のルールが定められており、会社の一方的な判断で不利益を受けることを防げます。
- ボーナスは法律上の義務ではないが慣例化している場合は保護対象になる
- 労働基準法第16条により返還請求は原則禁止されている
- 契約書や就業規則に反しない範囲での対応が合法
- 法的トラブルを防ぐには事前の確認と証拠の確保が有効
労働基準法と賞与の関係
ボーナスは法律で支給が義務付けられているものではありません。労働基準法には賞与に関する直接的な規定はなく、支給の有無や金額は会社の判断に委ねられています。ただし、労働契約や就業規則、社内慣習として継続的に支給されている場合には、法律上の「賃金」とみなされる可能性があります。
仮にボーナスが賃金と認定された場合、支給を拒否したり一方的に減額する行為は、労働基準法違反と判断されることもあります。たとえば、業績に関係なく全社員に毎年一定額を支給している会社で、退職予定者だけに支給しない場合、法的に問題になる可能性があります。
ボーナスが「業績に応じた特別手当」などの性質であれば、支給は会社裁量とされる場合が多く、支給額やタイミングが自由に決められることになります。どちらに該当するかは、過去の支給実績や契約書類で判断する必要があります。
ボーナス返還の強制性と違法性
すでに支給されたボーナスの返還を求められても、原則として応じる義務はありません。労働基準法第16条では、「労働契約に違反したことを理由に損害賠償や違約金を予定することはできない」とされています。ボーナスの返還を契約条項に盛り込んでも、それ自体が無効となる可能性があります。
退職を理由にボーナス返還を求める会社の言い分として、「直後に辞めるのは不誠実」「成果を出していない」などがありますが、それが法的に正当な理由と認められるかどうかは別の問題です。裁判例でも、明確な不正受給や虚偽申告がない限り、返還を認めた例は非常に少ないとされています。
ただし、就業規則や雇用契約に返還条件が詳細に定められており、かつ社員が同意している場合は、一定の返還義務が生じる可能性もあります。そのため、事前に自分がどのような契約内容で働いていたのかを確認しておくことが防御策になります。
法的トラブルを防ぐための知識と準備
退職とボーナスに関する法的トラブルを避けるためには、知識と事前準備が欠かせません。まず確認すべきは、就業規則と雇用契約書におけるボーナス支給の条件です。特に「支給日に在籍していること」「査定期間中に退職意向を示さないこと」などの要件が明記されていれば、それに沿った行動が求められます。
トラブルを未然に防ぐためには、以下のような準備が効果的です。
- 支給条件や在籍要件を記載した就業規則をコピーまたは保存する
- ボーナスに関する社内メールや通達を記録しておく
- 支給予定日と退職予定日を照らし合わせて計画を立てる
- 退職代行と綿密な日程調整を行い、会社とのやりとりを任せる
これらを準備しておくことで、会社側から不当な対応を受けた場合でも、証拠をもとに冷静に対処できます。特に金銭に関するトラブルは感情的になりやすいため、法律的な知識に基づいた行動を心がけることが大切です。信頼できる退職代行サービスや弁護士のサポートを得ることで、法的リスクを最小限に抑えることができます。
ボーナス受け取りにおすすめの退職代行サービスはこちら(当記事下)
ボーナス交渉可能な退職代行の選び方
ボーナス交渉を依頼したい場合は、退職代行サービスの中でも「交渉権限を持つ弁護士」が対応するサービスを選ぶことが必要です。一般の代行業者は書類提出や連絡代行は可能でも、賃金や賞与の交渉は法律で禁止されています。正しく選ばないと、ボーナス交渉ができずに損をする可能性があります。
- 交渉を行えるのは弁護士か労働組合だけ
- 民間業者は交渉できないためボーナス支給に影響する
- サービス内容と提供元の資格を確認して選ぶ
- ボーナス交渉実績や口コミも参考になる
弁護士対応サービスのメリット
弁護士が運営する退職代行サービスは、ボーナスの支給に関する「交渉」が可能です。労働問題に関する交渉や代理行為は、弁護士法によって弁護士のみが許可されており、民間業者では対応できません。
たとえば「退職後に支給予定だったボーナスが会社都合で止められた」などの場合でも、弁護士であれば法的根拠に基づいた主張ができるため、会社側も応じやすくなります。返還請求や支給条件に関するトラブルでも、代理人として直接対応してくれる点は安心材料です。
また、弁護士法人の退職代行は、書類作成や通知送付の形式も法律に則っているため、後々のトラブル防止にもつながります。費用はやや高めですが、ボーナスの金額が大きい場合は十分に見合う価値があります。
民間サービスの対応範囲と限界
民間業者が提供する退職代行は、ボーナスに関する交渉には対応していません。法的に「交渉」は弁護士の業務範囲とされているため、民間サービスでは「退職意思の伝達」や「連絡の仲介」にとどまります。
たとえば、ボーナスが支給されないという問題があっても、民間業者は「本人に確認してください」と伝えるだけで、支払い交渉や説明要求はできません。
 LiNee編集部
LiNee編集部退職手続き中に発生したトラブルについても、助言程度しか行えないため、トラブル発生時の対応力には限界があります。
ただし、費用は比較的安価で、即日対応やLINE相談などの手軽さがメリットです。退職に関する基本的な手続きだけをスムーズに進めたい人には向いていますが、ボーナスを確実に受け取りたい場合は慎重な判断が求められます。
自分に合った退職代行サービスを選ぶ基準
退職代行を選ぶ際は、「自分が何を目的にするのか」によって選択基準が変わります。ボーナス交渉を希望するなら、交渉権限を持つ弁護士か労働組合が提供するサービスを選ぶことが前提です。
| チェック項目 | 弁護士対応サービス | 民間サービス |
|---|---|---|
| ボーナス交渉の可否 | 法律に基づく交渉が可能 | 交渉不可 |
| 退職手続きの代行 | 包括的に対応 | 通知や連絡のみ |
| 法的トラブル対応 | 代理人として交渉・対応 | 助言のみ |
| 費用の目安 | 高め(3〜5万円以上) | 比較的安価(2〜3万円前後) |
| 相談方法 | 電話・メール・対面 | LINE・電話・メール |
| 実績・口コミでの信頼性 | 高(弁護士名の記載あり) | サイトによって差がある |
退職の目的が単に「すぐ辞めたい」なのか、「ボーナスをきちんと受け取って辞めたい」なのかで、選ぶべきサービスが変わります。
 LiNee編集部
LiNee編集部前者であれば民間業者でも対応可能ですが、後者なら弁護士対応を選ぶことでトラブルの不安を大幅に減らすことができます。
ボーナス受け取りにおすすめの退職代行サービスはこちら(当記事下)
ボーナスをもらってから退職するための準備
ボーナスを受け取ったうえでスムーズに退職するには、日程調整・証拠確保・事前の打ち合わせが不可欠です。在籍要件を満たし、トラブルなく支給を受けるためには、具体的な準備を進めることが成功のカギとなります。退職代行サービスを利用する場合でも、支給前の確認作業がとても重要です。
- 支給日を把握し、退職日を調整する
- 就業規則で在籍要件を確認する
- 退職代行と退職タイミングのすり合わせをする
- 支給に関する証拠資料を事前に集める
支給日と在籍条件をクリアする日程調整
ボーナス支給日と在籍要件を照らし合わせて、退職日を計画することが基本です。多くの企業では、賞与支給日当日に在籍していることが支給の前提となっています。
 LiNee編集部
LiNee編集部支給日が6月25日であれば、その日を含めて在籍していなければ受け取れないケースがあります。
日程調整を行う際には、過去の給与明細や就業規則を確認し、支給日を確実に把握しておく必要があります。支給後すぐに退職する予定でも、退職処理が完了するまで数日かかることもあるため、タイミングのズレがないように調整することが大切です。
退職代行を使う場合も、支給日に確実に在籍できるよう、退職の通知タイミングを調整してもらうよう依頼します。特に退職日が土日や祝日と重なると処理が翌営業日になることもあるため、カレンダーも確認して計画を立てると安心です。
退職代行との事前の綿密な打ち合わせ
退職代行を利用するなら、事前にボーナス支給に関する意図をしっかり共有しておく必要があります。退職日や連絡のタイミングがずれることで支給要件を満たせなくなる可能性があるため、希望する支給日や退職日を具体的に伝えることが重要です。
信頼できる退職代行サービスでは、退職希望者のスケジュールに合わせて柔軟に対応してくれます。ボーナス支給が確実であることを確認できるまでは、連絡を控えてもらうよう調整することも可能です。逆に、連絡が早すぎると、会社側から「支給対象外」と判断されてしまうリスクもあります。
 LiNee編集部
LiNee編集部ボーナス交渉や返還請求への対応が必要になる場合には、弁護士対応の退職代行を選ぶことで、より確実な対応が期待できます。
また、通常の民間代行では交渉行為ができないため、どの業者を選ぶかも計画段階で検討しておくことが望ましいです。
ボーナス受け取りにおすすめの退職代行サービスはこちら(当記事下)
ボーナス支給に関する証拠や資料を揃えておく
万が一のトラブルに備えて、ボーナス支給に関する情報や証拠を手元に残しておくことが大切です。就業規則や雇用契約書に記載された支給条件、過去の支給実績が記載された給与明細、社内通知などを保存しておくことで、トラブル発生時に有利に対応できます。
 LiNee編集部
LiNee編集部メールでのやり取りや社内のお知らせ文書は、支給日や在籍要件の根拠として有効です。支給予定日が不明確な場合は、人事部に問い合わせた結果を記録として残しておくと安心です。
退職代行を通じて交渉する場合でも、証拠の有無によって対応の幅が変わってきます。
資料が揃っていれば、会社側が「支給対象外」と主張した場合でも反論がしやすくなります。トラブルを未然に防ぎ、確実にボーナスを受け取ってから退職するために、証拠の準備は事前に行っておくと安全です。
退職代行でボーナスを受け取った人たちの体験談
退職代行を利用しても、正しい準備とタイミングを押さえればボーナスをきちんと受け取ることができます。実際にサービスを活用して退職し、ボーナスを受け取れた人たちの声には、成功と失敗の両方から学べるポイントがあります。事前準備の有無や、退職日と支給日の調整が結果を左右しています。
- 支給条件を事前に確認して満額受け取れたケースがある
- 査定期間と支給日の誤認で損をした例もある
- 退職代行との打ち合わせ内容が結果に大きく影響する
- 証拠の保存や社内規定の理解が支給を後押しした体験もある
ボーナス満額支給で円満退職できた成功例
退職代行を使うのは正直不安でしたが、事前に支給日と在籍要件を確認しておいたおかげで満額ボーナスをもらえました。会社の就業規則には『支給日に在籍していること』と書かれていたので、退職代行には支給日を過ぎてから手続きを開始してもらいました。おかげでトラブルもなく、スムーズに退職できました。
支給日を過ぎた直後に退職意向を伝えたので、会社からも何も言われませんでした。担当の退職代行の方がスケジュールをしっかり組んでくれたので、本当に安心して任せられました。準備とタイミングが何より大切だと実感しました。
支給条件を誤解して損した失敗例
夏のボーナスが出ると聞いていたので、そのタイミングで退職代行を使いました。でも、あとから支給日当日に在籍していないと支給されないことを知って、結局ボーナスはもらえませんでした。就業規則を確認せずに動いたのが間違いでした。
評価期間が過ぎていれば大丈夫だと思っていたけど、査定の影響があるからといって金額を減らされてしまいました。もう少し待っていれば満額出たかもしれないと後悔しています。事前にもっと調べておけばよかったです。
事前準備と知識の重要性を実感したケース
退職代行にお願いする前に、ボーナスに関する条件を全部チェックしました。雇用契約書に支給日と査定期間が書かれていて、それをもとに日程を調整しました。支給日後の勤務記録や給与明細も保存しておいたので、会社から問い合わせがあってもすぐに対応できました。
ネットで調べた情報だけでなく、実際に社内の人事にさりげなく支給日を聞いておいたのが良かったです。その情報をもとに退職代行とやり取りして、的確なタイミングで退職できました。トラブルを防げたのは準備の差だったと思います。
弁護士対応の退職代行を使ったので、万が一ボーナスが支給されなかった場合でも、交渉してくれるという安心感がありました。結局問題なく支給されましたが、法律のプロが対応してくれるというのはとても心強かったです。
ボーナス受け取りにおすすめの退職代行サービス5選
ボーナスを確実に受け取ってから退職したい場合は、信頼できる退職代行サービスを選ぶことが不可欠です。
 LiNee編集部
LiNee編集部退職のタイミングや会社とのやり取りに配慮が必要な場面では、法的知識や経験のあるサービスが安心につながります。
以下は、ボーナス支給後のスムーズな退職に対応してくれる実績のあるサービスを厳選した5社です。
- ボーナス支給のタイミング調整に柔軟な対応が可能
- 就業規則や契約内容に合わせたアドバイスが受けられる
- 法的トラブルに対応できる弁護士対応サービスもある
- 即日対応・相談無料などサポート体制が整っている
退職代行ガーディアン

労働組合が運営しており、企業との交渉が法的に可能な数少ない退職代行サービスです。就業規則に沿った対応や、ボーナス支給の条件確認を含むアドバイスも受けられます。365日対応で、深夜や早朝でも相談できる点が利用者に好評です。
料金は一律24,800円(税込)で追加料金は一切なく、労働問題に詳しい専門スタッフが担当します。交渉権限があるため、企業側に対して明確にボーナス支給日までの在籍確認なども伝えられます。
| 運営タイプ | 労働組合 |
|---|---|
| 料金 | 24,800円(税込) |
| 支払タイミング | 前払い |
| 追加料金 | なし |
退職代行ガーディアンの基本情報
| サービス名 | 退職代行ガーディアン |
|---|---|
| 運営会社名 | 合同労働組合ガーディアン |
| 料金 | 一律24,800円(税込) |
| 返金保証 | 記載なし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込 クレジットカード(VISA、Mastercard) |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 退職の意思を会社へ伝達 有給消化や未払い賃金の交渉 即日対応可能 |
| 特徴 | 労働組合運営で交渉力あり 追加料金なしの明確な料金体系 24時間365日対応 |
| メリット | 低価格で高品質なサービス 即日退職が可能 |
| 監修者 | 記載なし |
| 公式サイト | https://taisyokudaiko.jp/ |
退職代行Jobs

運営元が労働組合と提携しており、安心して交渉を任せられるのが特徴です。LINEでのやり取りに対応しており、勤務中でも隙間時間で準備を進められます。相談は何度でも無料で、即日対応も可能です。
料金は27,000円(税込)と比較的リーズナブルで、追加費用がかからない点も魅力です。退職日や連絡のタイミングを細かく調整してくれるため、ボーナス受給後の退職を希望する人には相性のよいサービスです。
| 運営タイプ | 労働組合 |
|---|---|
| 料金 | 27,000円(税込)~ |
| 支払タイミング | 前払い 後払い |
| 追加料金 | なし |
退職代行Jobsの基本情報
| サービス名 | 退職代行Jobs |
|---|---|
| 運営会社名 | 株式会社アレス (合同労働組合ユニオンジャパン) |
| 料金 | 27,000円(税込) +労働組合費2,000円 |
| 返金保証 | あり |
| 後払い | 可能 |
| 支払方法 | 銀行振込 クレジットカード コンビニ決済 現金翌月払い |
| 退職成功率 | 非公開 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| サービス内容 | 退職の意思を 会社に伝達 |
| 特徴 | 労働組合と提携し 会社と交渉可能 |
| メリット | 即日退職が可能で 引き止められない |
| 監修者 | 弁護士 西前啓子 |
| 公式サイト | https://jobs1.jp/ |
退職代行みやび

弁護士法人が直接運営しており、法的な交渉やトラブルにも対応できる退職代行です。ボーナスの返還請求や支給トラブルなどにも、弁護士が代理人として対応可能です。
弁護士が対応するサービスのため、費用は27,500円(税込)〜とやや高めですが、その分、法的根拠に基づいた対応が受けられます。賃金未払いへの請求も依頼可能で、安心して任せられる実績があります。
| 運営タイプ | 弁護士法人 |
|---|---|
| 料金 | 正社員・契約社員:27,500円(税込) 公務員:55,000円(税込) 自衛隊・業務委託・会社役員:77,000円(税込) |
| 支払タイミング | 記載なし |
| 追加料金 | なし |
退職代行みやびの基本情報
| サービス名 | 退職代行 弁護士法人みやび |
|---|---|
| 運営会社名 | 弁護士法人みやび |
| 料金 | 正社員・契約社員:27,500円(税込) 公務員:55,000円(税込) 自衛隊・業務委託・会社役員:77,000円(税込) |
| 返金保証 | 記載なし |
| 後払い | 記載なし |
| 支払方法 | 銀行振込 クレジットカード |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 弁護士が直接退職手続きを代行 会社への連絡 退職届の提出 未払い給与・有給休暇の請求 退職後のサポート |
| 特徴 | 法的知識に基づく 適切な対応 |
| メリット | 有給消化や未払い給与の 交渉も可能 |
| 監修者 | 弁護士法人みやび |
| 公式サイト | https://taishoku-service.com/ |
退職代行OITOMA

柔軟なサポートとスピード対応が強みで、相談後すぐに手続きを進められるサービスです。労働組合と連携しているため、交渉も可能です。LINEや電話での連絡もスムーズで、在籍条件や支給日を踏まえた日程調整にも対応しています。
料金は24,000円(税込)〜と比較的安価でありながら、希望に応じてスケジュールを丁寧に確認してくれる姿勢に定評があります。口コミでも「初回のヒアリングが丁寧だった」と好評価が多く寄せられています。
| 運営タイプ | 労働組合 |
|---|---|
| 料金 | 24,000円(税込) |
| 支払タイミング | 前払い 後払い |
| 追加料金 | なし |
退職代行OITOMAの基本情報
| サービス名 | 退職代行 OITOMA(オイトマ) |
|---|---|
| 運営会社名 | 株式会社H4 |
| 料金 | 24,000円(税込) |
| 返金保証 | 退職できなかった場合、全額返金保証 |
| 後払い | 可能(手数料5,000円、最長1ヶ月以内の支払い) |
| 支払方法 | 現金、クレジットカード |
| 退職成功率 | 100% |
| 対応地域 | 全国 |
| サービス内容 | 退職手続きの代行 会社への連絡代行 退職届の作成サポート |
| 特徴 | 労働組合と提携 24時間365日対応 追加料金なし |
| メリット | 即日退職が可能 全額返金保証で安心 |
| 監修者 | 行政書士東京中央法務オフィス |
| 公式サイト | https://o-itoma.jp/ |
退職代行リーガルジャパン

法務の知識を活かした丁寧な対応が特徴の退職代行サービスです。弁護士事務所と連携しており、トラブルになった際も専門家によるサポートが期待できます。ボーナスの支給要件などに関する相談にも柔軟に対応します。
料金は25,000円(税込)〜で、プランによっては書類作成や企業対応などもセットになっています。退職までの流れを一括サポートしてくれるので、はじめて退職代行を利用する人でも安心です。
| 運営タイプ | 労働組合 |
|---|---|
| 料金 | 25,000円(税込) ※別途、労働組合加入費2,000円が必要 |
| 支払タイミング | 前払い |
| 追加料金 | なし |
退職代行リーガルジャパンの基本情報
退職代行利用時のボーナスについてよくある質問(FAQ)
- 退職代行を使ってもボーナスは必ずもらえますか?
-
退職代行を利用したからといって、必ずしもボーナスが支給されるわけではありません。ボーナスの支給には、会社ごとに決められた支給条件(例:支給日に在籍していること、査定期間中の勤務実績など)があり、それを満たしていない場合は支給されないことがあります。退職代行の利用自体が理由で不支給になることは原則ありませんが、就業規則や雇用契約書に明記された条件を事前に確認することが必要です。
- ボーナス支給日に在籍していれば、満額もらえますか?
-
在籍要件を満たしていても、満額支給されるとは限りません。ボーナスの支給額は、査定期間中の勤務態度や業績、評価に基づいて決定される場合が多いため、退職の意向を示していたり評価が下がっていた場合は減額される可能性があります。また、査定期間中にすでに退職を申し出ていると、評価にマイナスが反映されることもあります。
- ボーナス支給後すぐに退職すると問題になりますか?
-
支給後すぐの退職は、会社によっては快く思われないことがありますが、法的には問題ありません。ただし、退職のタイミングによっては会社から「返還請求」されるケースもあります。ただし、労働基準法第16条により、退職を理由とした違約金や損害賠償の請求は原則認められていません。返還に応じる義務は基本的にないと考えられています。
- 退職代行にボーナスの交渉はお願いできますか?
-
ボーナスの交渉ができるのは、弁護士か労働組合の退職代行サービスに限られます。一般の民間業者は、退職の意思表示などの「伝達」は行えますが、「交渉」には法的な制限があるため対応できません。ボーナスに関する未払い・返還問題や交渉を依頼したい場合は、弁護士対応の退職代行を選ぶ必要があります。
- 支給されるはずだったボーナスが退職を理由に止められました。取り戻せますか?
-
就業規則や雇用契約で明確にボーナス支給が規定されており、かつ支給要件を満たしていた場合は、不支給に対して法的に異議を申し立てることが可能です。ボーナスが毎年恒常的に支給されており、賃金としての性質があると認められる場合、未払いは違法とされる可能性があります。証拠をそろえたうえで、労働基準監督署や弁護士に相談するのがよいでしょう。
- 退職代行の利用は査定に影響しますか?
-
退職代行の利用自体が査定に影響することはありません。しかし、査定期間中に退職意向を示した場合、それを理由に評価が下がる可能性があります。評価が低くなれば、その分ボーナスが減額されるリスクがあります。退職代行の使用とは無関係でも、退職のタイミングが評価に影響を与える点は考慮しておく必要があります。
- 就業規則が手元になくても支給条件は確認できますか?
-
基本的には就業規則は社員が確認できるように会社が保管・開示しているはずです。社内ポータルや人事部に問い合わせることで閲覧が可能な場合が多く、確認を拒まれることはありません。また、過去の給与明細や支給実績から傾向を把握することもできます。退職代行を利用する場合でも、事前に支給条件を確認しておくことでトラブルを回避しやすくなります。
- 支給されたボーナスの返還を会社から求められたら応じなければなりませんか?
-
原則として、支給されたボーナスの返還請求には応じる必要はありません。労働基準法第16条で「賠償予定の禁止」が定められており、退職を理由に支払われた賃金やボーナスの返還を強制することはできません。ただし、雇用契約書に特別な条件が書かれていた場合や、不正受給があったと認められる場合は例外となることもあります。
- 査定期間と支給日がずれているとボーナスはどうなりますか?
-
査定期間と支給日は一致しないことが多く、ボーナスは過去の勤務状況をもとに決定されます。たとえば、6月に支給されるボーナスは、前年12月から当年5月の働きぶりをもとに査定されるといった形です。そのため、査定期間中に退職の意思表示をしていると、その評価が支給額に影響することがあります。退職日を決める際には、査定終了後かつ支給日後がベストといえます。
- ボーナス支給後、どれくらい間を空けて退職すれば安心ですか?
-
最低でも支給日から2〜3営業日以上の在籍期間を設けて退職するのが安心です。支給処理の関係で、支給日当日に退職連絡をすると処理上「退職済み」とされてしまうケースがあり、支給漏れにつながるおそれがあります。確実に支給を受けたい場合は、支給を確認してから数日空けて退職の手続きを進めるのが安全です。
まとめ
退職代行を利用してもボーナスを受け取るための方法や注意点について詳しく説明しました。退職代行を利用することで、直接会社に退職を伝えることなく、スムーズに退職手続きを進めることができます。
退職代行を利用して退職手続きを完了した後も、適切なフォローアップが重要です。退職手続きの確認、次のステップの準備、アフターサポートの活用など、退職後の生活を安定させるための取り組みを行いましょう。
退職代行を利用することで、退職に伴うストレスやトラブルを軽減し、円滑に退職手続きを進めることができます。信頼できる業者を選び、適切な準備と対応を行うことで、安心して新しいスタートを切ることができるでしょう。